山車の構造
更新日:2023年10月10日
山車の構造
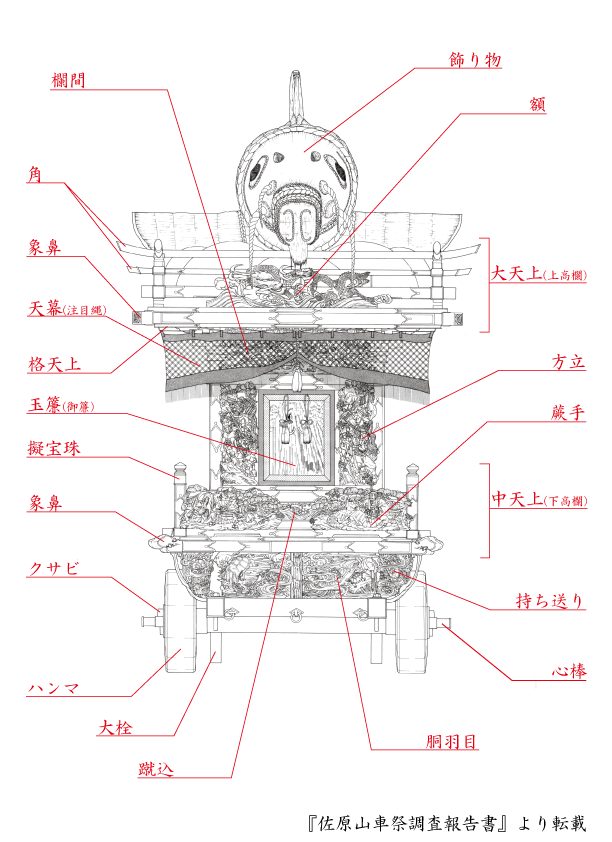
上仲町区

山車
制作年…明治34年(1901)
飾物
題…太田道灌
制作年…大正10年(1921)
人形師…大柴徳次郎
山車額
題…徳威(とくい)
制作年…大正10年(1921)
揮毫…野村
彫刻
題…二十四孝
制作年…大正11年(1922)
彫工…佐藤光正、光清ほか
一口メモ
天幕は金糸に編み目。文化時代(1804~1817)の作。文化財としての価値も高い。
荒久区

山車
制作年…昭和3年(1928)
飾物
題…経津主命
制作年…大正9年(1920)
人形師…三代目 安本亀八
山車額
題…威徳(いとく)
制作年…不明
揮毫…中尾紫水
彫刻
題…獅子群遊
制作年…安政年間(1854~1860)
彫工…後藤茂右衛門正忠
一口メモ
飾り物は香取神宮の祭神。彫り物も立派で、特に方立(柱隠し)は優れている。
本川岸区

山車
制作年…明治15年(1882)
飾物
題…天鈿女命
制作年…文化元年(1804)(戦後大修復)
人形師…鼠屋五兵衛
山車額
題…咲樂(しょうらく)
制作年…大正5年(1916)
揮毫…平田盛胤(神官、国学者)
彫刻
題…仁徳天皇、神功皇后他
制作年…明治14年、明治16~33年
彫工…後藤一重(藤太郎)、小松重太郎(初代光重)
一口メモ
他の山車と異なり天井が神楽殿で天鈿女命が舞う優雅な形を取り入れている。
八日市場区

山車
制作年…明治29年(1896)
飾物
題…鯉
制作年…文久年間(1861~1863)
制作者…町内住民
山車額
題…龍の彫刻
制作年…不明
彫工…小松重太郎光重
彫刻
題…太閤記武将ノ図
制作年…明治21年
彫工…小松重太郎光重・光春
一口メモ
飾り物の鯉は、麦わらを使い、町内全員の協力で制作。
浜宿区

山車
制作年…平成9年(1997)新造
飾物
題…武甕槌命
制作年…昭和12年(1937)
人形師…鼠屋
山車額
題…柔和(にゅうわ)
制作年…不明
揮毫…元龍
彫刻
題…唐獅子牡丹、鳴神、竹林七賢人獅子の子落し
制作年…嘉永元年(1848)~嘉永4年(1851)
彫工…後藤茂右衛門正綱
一口メモ
山車彫刻は嘉永元年から4年間かけて制作されたもの。
寺宿区

山車
制作年…嘉永3年(1850)
飾物
題…金時山姥
制作年…明治12年(1879)
人形師…鼠屋 福田萬吉
山車額
題…幣臺(へいだい)
制作年…不明
揮毫…不明
彫刻
題…登り龍と下り龍
制作年…嘉永3年(1850)
彫工…三代目 石川常次郎
一口メモ
飾り物は足柄山での少年期を表し、熊にまたがり斧をかざし、力強さを表している。
田宿区

山車
制作年…嘉永4年(1851)
飾物
題…伊弉那岐尊
制作年…明治43年(1910)
人形師…面六
山車額
題…雍泰(ようたい)
制作年…不明(1910)
揮毫…並木栗水(漢学者)
彫刻
題…唐子遊びなど
制作年…安政3年(1856)~5年(1858)
彫工…十代目 後藤茂右衛門正忠
一口メモ
山車は漆塗りで、天井には漆蒔絵を施してある。
仁井宿区

山車
制作年…平成11年(1999)新造
飾物
題…鷹
制作年…宝暦年間(1751~1764)
制作者…町内住民
山車額
題…仁愛(じんあい)
制作年…昭和11年
揮毫…島崎千涯
彫刻
題…松に鷹、唐獅子牡丹など
制作年…江戸後期
彫工…不明
一口メモ
飾り物の鷹は、稲わらを使い、町内全員の協力で制作。
船戸区

山車
制作年…平成9年(1997)新造
飾物
題…神武天皇
制作年…明治20年(1887)
人形師…三代目 原舟月
山車額
題…烝衎(じょうかん)
制作年…江戸中期
揮毫…久保木蟠龍(儒学者)
彫刻
題…源頼光と四天王の大江山酒呑童子退治の図、米づくり収穫の秋の図
制作年…江戸時代
彫工…石川常次郎
一口メモ
彫り物に良いものが多いが、中でも鯉の彫り物が優れているという。
下仲町区

山車
制作年…文政5年(1822)
飾物
題…菅原道眞(菅公)
制作年…大正10年(1921)
人形師…三代目 安本亀八
山車額
題…頌徳(しょうとく)
制作年…不明
揮毫…不明
彫刻
題…山伏の図
制作年…大正9年(1920)
彫工…後藤桂林
一口メモ
玉簾、天幕は安政3年(1856)の作。平成24年、古文書の発見により、現存する佐原最古の山車と判明した。
仲川岸区

山車
飾物
題…神武天皇
制作年…明治31年(1898)
人形師…湯本長太郎
山車額
題…博天如(ひろきことてんのごとし)
制作年…明治31年(1898)
揮毫…巌谷修(書家)
彫刻
題…米づくり
制作年…明治31年(1898)
彫工…後藤直政
一口メモ
三方正面造りの山車で、通し柱8本で制作。材料の欅(けやき)は九州の玉目の一本取り。
下川岸区

山車
制作年…明治31年(1898)
飾物
題…建速素盞嗚尊
制作年…江戸時代後期
人形師…不明
山車額
題…宏遠(こうえん)
制作年…明治34年(1901)
揮毫…源童通禧(東久世通禧)
彫刻
題…日本神話
制作年…文久年間
彫工…佐藤光正
一口メモ
山車は「八方にらみ」といわれる形で四方向のどちらから見ても同じ様に見える。
上中宿区

山車
制作年…嘉永5年(1852)
飾物
題…鎮西八郎為朝
制作年…明治15年(1882)
人形師…鼠屋 福田万吉
山車額
題…富士山の彫刻
彫刻
題…源頼朝の富士の巻狩り絵巻
制作年…嘉永2年~4年(1849~1852)
彫工…立川録三郎
一口メモ
彫り物は「柱隠し」といわれる技法が用いられ、富士の裾野での巻き狩りの様子が彫られている。
下宿区

山車
制作年…明治8年(1875)
飾物
題…源頼義
制作年…明治32年(1899)
人形師…古川長延
山車額
題…誠意(せいい)
制作年…明治15年(1882)
揮毫…柳田正斉(儒学者)
彫刻
題…平家物語
制作年…明治8年(1875)
彫工…石川三之介、後藤源兵衛、左利重吉、後藤桂林
一口メモ
飾り物は、源頼義が山中の戦いで、岩を弓で砕き水を出した故事による。
東関戸区

山車
制作年…昭和10年(1935)
飾物
題…大楠公(楠木正成)
制作年…昭和10年(1935)
人形師…大柴護豊
山車額
題…純正(じゅんせい)
制作年…昭和10年(1935)
揮毫…荒木貞夫(陸軍大将)
彫刻
題…太平記など
制作年…昭和10~26年(1935~1951)
彫工…金子光清、池田信之
一口メモ
山車は、柱隠しがなく四方正面を特徴とする。額の文字は荒木貞夫陸軍大将の筆。
西関戸区

山車
制作年…昭和10年(1935)
飾物
題…瓊瓊杵尊
制作年…昭和15年(1940)
人形師…鼠屋
山車額
題…神威赫奕(しんいかくえき)
制作年…昭和10年(1935)
揮毫…有馬良橘(海軍大将)
彫刻
題…龍、獅子群遊、唐子
制作年…嘉永年代(1848~54)
彫工…四代目 石川藤吉朝光
一口メモ
額は石川朝光作の彫り物で飾られ、文字は明治神宮の元宮司 有馬良橘氏の筆。
上新町区

山車
制作年…昭和11年(1936)
飾物
題…諏訪大神
制作年…昭和11年(1936)
山車額
題…敬神(けいしん)
制作年…昭和11年(1936)
揮毫…島崎千涯
彫刻
題…切り抜きの龍
制作年…昭和11年(1936)
彫工…成毛哲太郎
一口メモ
大榊を飾り、八咫鏡(やたのかがみ)の両側に旗などが置かれている。
北横宿区

山車
制作年…明治8年(1875)
飾物
題…日本武尊
制作年…明治8年(1875)
人形師…鼠屋 福田万吉
山車額
題…愛國(あいこく)
制作年…不明
揮毫…柳田正斉
彫刻
題…猿田彦命と楽人、天照大神、源頼朝の放生会と千羽鶴など
制作年…明治8年(1875)
彫工…岸上定吉、塙正明、石川常治郎
一口メモ
総欅(けやき)造りの山車。彫刻は木彫りとは思えない立体感と生命力に溢れている。
下新町区

山車
制作年…江戸末期
飾物
題…亀と別れる浦嶋太郎
制作年…明治12年(1879)
人形師…鼠屋 福田万吉
山車額
題…恩波(おんぱ)
制作年…明治中期
揮毫…源喬(みなもとたかし)
彫刻
題…水滸伝(下絵・歌川国芳)
制作年…文久2年(1862)
彫工…石川三之助
一口メモ
天幕は金箔のしめ縄。彫り物は歌川国芳の水滸伝をかたどり、彫りも深く重厚な感じである。
新上川岸区

山車
制作年…令和5年(2023)
飾物
題…牛天神(菅原道真)
制作年…江戸末期
人形師…不明
山車額
題…上河岸(うわがし)
制作年…安政4年(1857)
揮毫…高階慎(書家)
彫刻
龍、獅子、鷹、登龍、蓑亀などの縁起動物 源氏武将の勇壮な場面
制作年…嘉永元年(1848) 嘉永3年(1850) 明治8年(1875)大正4年(1915)
彫工…石川常次郎 石川三之助 岸上定吉 小松重太郎(初代光重) 和泉義明
一口メモ
蕨手の彫り物は、保元・平治の乱で功を立て、剃髪して源三位入道と名のった源頼政の図柄。
南横宿区

山車
制作年…明治8年(1875)
飾物
題…仁徳天皇
制作年…大正14年(1925)
人形師…三代目 安本亀八
山車額
題…高きやに登りて見れば烟(けむり)たつ民のかまどはに賑いにけり
制作年…不明
揮毫…不明
彫刻
題…三国志、龍
制作年…明治9~19年(1876~86)
彫工…後藤一重
一口メモ
彫刻は三国志「桃園の誓い」から始まり、名場面を10年の歳月をかけて彫り上げた大作である。
上宿区

山車
制作年…昭和53年(1978)
飾物
題…源義経
制作年…昭和55年(1980)
人形師…面六・四代目 田口義雄
山車額
題…智勇(ちゆう)
制作年…昭和55年(1980)
揮毫…白井永二(神官)
彫刻
題…獅子の子落し、唐獅子牡丹、島千鳥
制作年…嘉永年間(1848~1853)
彫工…石川虎次郎
一口メモ
飾り物は、源平の戦いのひよどり越での勇姿をかたどっている。
新橋本区

山車
制作年…明治27年(1894)
飾物
題…小野道風
制作年…明治4年(1871)
人形師…鼠屋 福田万吉
山車額
題…雲龍(うんりゅう)
制作年…不明
揮毫…小野道風(真筆を彫ったもの)
彫刻
題…雌雄の龍
制作年…平成2年(1990)
彫工…岡野繁(宮大工)
一口メモ
額の文字「雲龍」は小野道風真蹟と伝えられている。
下分区

山車
制作年…明治28年(1895)
飾物
題…小楠公(楠木正行)
制作年…昭和10年(1935)
人形師…大柴護豊
山車額
題…下分(しもわけ)
制作年…明治28年(1895)
揮毫…青野逸山
一口メモ
飾り物は四条畷の合戦の際、如意輪寺の壁に矢尻で辞世の句を書きつける楠木正行の姿。
中宿区

山車
制作年…江戸時代後期
飾物
題…桃太郎
制作年…大正11年(1922)
人形師…三代目安本亀八
山車額
題…豐禋(ほうえん)
制作年…明治中期と昭和初期の二基
揮毫…柳田正斉
彫刻
題…竜宮城、竜、戦国絵巻
制作年…江戸時代後期
彫工…不明
一口メモ
昭和30年代を最後に、現在山車の曳き廻しは行われていない。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
このページの作成担当
商工観光課 観光班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212
ファクス:0478-54-2855

